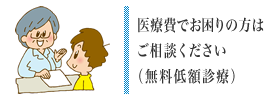医療・福祉関係者のみなさま
2010年8月16日
相談室日誌 連載311 病院と在宅スタッフの連携で 野澤 由香 (福岡・たたらリハビリテーション病院)
緩和ケア病棟に胃がん末期のAさん(七〇代)が転院してきたのは昨年の秋。アルコール性の認知症もあり、警戒心を秘めた上目遣いの、くるくるした目が印 象的な小さなおじいさんでした。生活保護受給者で結婚歴はなく、長年風呂なしトイレ共同の古い長屋に一人住まいでした。入院前は失禁状態で部屋は汚れ、栄 養も十分でなく衰弱していました。
Aさんは転院して来たとたん荷物を持って「帰ります」と。引き留める私たちスタッフの努力も空しく、かたくなでした。しかたなくケアマネジャーに連絡し、最短コースでサービス調整をしてもらい家に帰りました。
ところがAさんは、痛みが出るとタクシーで突然病院に現れます。無銭乗車で来ることもありました。あわてて入院の手配をしたら、その日の午後に帰ってし まうなど、いろいろ問題はありましたが、その都度、主治医や在宅スタッフは温かく対応しました。
その後、Aさんの長屋は取り壊すことになり、食事つきアパートに転居しました。しかし、Aさんにとっては退去した長屋が我が家で、新しいアパートには馴染めず、再入院した後は、もう帰宅願望はなくなりました。
寂しそうなAさんを見た主治医の提案で、Aさんを連れて主治医とSWで長屋の跡地やヘルパー事業所、デイサービス、ケアマネ事業所などを巡るツアーに出 かけました。Aさんはなつかしい人たちとの再会をとても喜んでいました。それから二カ月後、最後までタバコや食事を楽しみ、緩和ケア病棟のスタッフに見守 られて、旅立ちました。
お通夜にはヘルパーさんたちも来てくれ、涙を流しながら、私たちにAさんの思い出話を聞かせてくれました。Aさんは、家族はなくても、かかわった人びとに愛されました。
Aさんを通じて、私たちにも温かい連帯感が生まれました。病院と在宅のスタッフが常に一体となって、「困ったな」「どうしよう」を共有し、話し合いなが ら対応してきました。在宅部門との連携プレーがあったから、Aさんの希望に沿えるサポートができたと思います。頼りがいのある在宅部門のスタッフに感謝し つつ、私たちSWも病院の受け入れ窓口として、地域に根を張っていきたいと思います。
(民医連新聞 第1482号 2010年8月16日)
 この記事を見た人はこんな記事も見ています。
この記事を見た人はこんな記事も見ています。