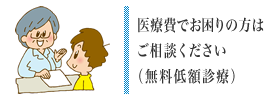医療・福祉関係者のみなさま
2011年2月7日
フォーカス 私たちの実践 ALS患者の支援 東京 にしたま訪問看護ステーション 気管切開で“生きる”を選択 可能性を信じ根気強く寄り添う
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の中には、「家族に長く介護の負担をかけたくない」と考えて、気管切開をして生き続けることに 抵抗を感じる人もいます。訪問看護師が患者本人と家族に寄り添い、「気管切開をして生きる」という選択を引き出した事例について、第一〇回看護介護活動研 究交流集会で、にしたま訪問看護ステーションの鈴木夏江さんが報告しました。
当ステーションの患者Aさんは四〇代でALSと診断されました。診断当時、娘三人は小学生と中学生で、Aさんは発症後もエンジニアとして仕事を続けました。診断七年目で寝たきりになり、訪問看護の依頼がありました。
Aさんは訪問当初、ケアに強いこだわり(願い)がありました。例えば、呼吸苦のため鼻マスク式の人工呼吸器を装着していましたが、トイレに行くことにこ だわりました。トイレまで移動する際はマスクを外すため、独自の呼吸介助法で呼吸を確保し、ヘルパーと看護師二人がかりで移動しました。移動は重労働のう え転落の危険性もあります。何度もケアの方法を変えることを提案しましたが、拒否されました。
また、「家族に負担をかけたくない」との思いから、「自分が死んだ後の売却に困るので、住宅改修はしない」「食事や会話の楽しみを失いたくないので、胃 ろうは造らない、気管切開もしない」と話していました。
Aさんを変えた5年の歳月
Aさんの妻は介護に不慣れなうえ思春期の子どももおり、精神的に追いつめられていました。私たちは病院在宅支援室や在宅医、ほかの訪問看護ステーション、ヘルパー事業所、ケアマネなどと地域ケアチームを組み、何度も話し合いを重ねてチームでささえました。
訪問開始から五年間は大きなトラブルもなく生活できましたが、ALSが進行し肺炎になって救急搬送され、気管切開(気切)の決断を迫られる時がやってきました。
以前はかたくなに気切を拒んでいましたが、五年という歳月の中で考えを変えました。Aさんは「気切してもいいが、自分では決められない」と家族に判断を 委ねました。家族は「気切して痰が取れれば、いつものお父さんに戻るのに、このまま終わりになんてできない」と気切を選びました。
Aさんが考えを変えた背景には、鼻マスク式の呼吸器を装着してきた五年間があります。家族がいっしょに過ごすことで、Aさんは障害を受容し、家族も介護に慣れ精神的にも余裕ができました。
また、長女が看護大学に進学して生きがいができたこと。患者会の情報交換で気切後の生活がイメージできたことも、気切に踏み切る動機になったと思いま す。家族にとって展望の見えない困難な時期も寄り添い続けた私たちへも「気切後も、これまでと変わらず支えてくれるはず」との信頼感があったと思います。
ブログで生活をつづる
気切したAさんは声を失い文字盤と口話による会話になり、コミュニケーションをはじめ、胃ろうの管理、気管内吸引などさまざまな課題があります。地域ケアチームは「Aさんの生活を守る」という共通目標のもと、気切後も工夫してケアを構築しています。
私たちは、Aさんのケアを通して、人間はあらゆる環境の変化に適応する能力があり、そのプロセスを時間をかけて歩むことで、展望を開くことができること を学びました。今、当ステーションは四人のALS患者を担当していますが、この学びを活かしています。
Aさんは現在、唇のかすかな動きでパソコンを操作し、ブログを立ち上げて日々の思いをつづっています。Aさんの豊かな人間性にふれ、生きてほしいと願っ ていた私たちは、Aさんと家族の選択を歓迎しこれからもいっしょに歩んでいく覚悟です。
(民医連新聞 第1493号 2011年2月7日)
 この記事を見た人はこんな記事も見ています。
この記事を見た人はこんな記事も見ています。