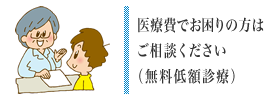健康・病気・薬
2014年4月7日
フォーカス 私たちの実践 認知症利用者に生きがいを 島根・松江生協 リハビリテーション病院 認知症の利用者さんととりくむ「料理倶楽部」
急性期の治療やリハビリが一段落し、“生活の場”としての色合いも濃い療養病棟。島根・松江生協リハビリテーション病院療養病棟 では、認知症の利用者さんにも、楽しみや生きがいを持って生活してほしいと、「料理倶楽部」を発足させました。効果あり。参加者は年々増え、現在は三つの 倶楽部に発展しています。
料理倶楽部を始めたのは二〇一一年。職員同士で事例検討会や学習会を重ねるなかで、やってみようという声があがりました。「利用者さんは女性が多 いので、女性にもっとも身近で、生活の記憶も多い“料理”なら、参加しやすいのではないかと考えた」と話すのは、当時の責任者だった太野垣(たやがき)ひ ろむさん(介護福祉士)。倶楽部の活動は、月に一回、二時間。主に、認知症高齢者日常生活自立度軽中度の女性利用者を対象に、四~五人でスタートしまし た。
身体が覚えている
利用者の多くは、かなり前から台所を家族に任せていたり、病気を機に料理から離れていたりして、はじめは「何もできん」「手の力がないから」と尻 込みしていました。が、ひとたび包丁を握ると、素早く調理を始めたり、視力の落ちた利用者が手際よく野菜の皮をむいたり、普段は腰が九〇度に曲がった人の 背筋が伸びるなどの変化がありました。
「自分がいた場を思い出し、動き出すようでした。身体が覚えているんですね。食事は、幼いころや若かったころの楽しい記憶とつながっていることも多く、 昔のことを思い出しながら調理する姿は自信にあふれていて、笑顔も多く見られました」と太野垣さん。「もう何年も料理はしていない」と話していた人が、自 分で作ったものをみんなで食べながら、懐かしい家庭料理や仕事の話をするようになりました。また、普段はミキサー食を食べている人が、この時は普通食をむ せることなく食べられました。
楽しい食事風景を見て、「私も参加したい」という人が出てきたり、共同組織の人が積極的にボランティアをするなど、交流の場としても広がっていきました。
利用者を見る目が変化
倶楽部を続ける中で、職員の利用者を見る目も変化しました。佃真理子さん(介護福祉士)は、「多くの利用者さんは、『病気になってしまったから、 自分は何もできない』『人にやってもらうしかない』と思い込んでいます。でも、重い認知症の人が、包丁を握ると見事に魚をさばいたりします。料理という生 活に結びついた経験を通じて、普段はかなりの介助が必要な利用者さんでも、工夫や働きかけ次第でもっとできることを、私たちも学びました」。
利き手が麻痺している利用者が、動かせる方の手で包丁を持ち、職員に食材を押さえてもらいながら一生懸命切り、「自分の手が戻ったみたい」と喜んだり、 「今度はいつ?」と心待ちにしたり…。予定が覚えられない人も多いので、倶楽部の日が近づくと手作りの「お知らせカード」を配布。最初はしぶしぶ参加して いた利用者が、「お知らせカード」を握り、時間になると自分からやってくるようにもなりました。
利用者の様子は継続して記録。その中で、食事がうまく食べられない高次脳機能障害の利用者が、実は食べ物を「すくって口に運びたい」という想いがあることが分かるなど、利用者の理解がすすんだこともあります。
* *
現在、参加希望者が増え、料理倶楽部は内容別に三つに発展しています。一汁三菜で、昼食を一食丸ごと作る「料理倶楽部」、職員やボランティアの手 伝いで一品作るのが目標の「ゆるゆる料理倶楽部」、味噌汁を作る「味噌汁倶楽部」です。次回のメニューは、参加者全員で決めます。
「季節や歳時のメニュー、その土地ならではのメニューなど、患者さんから職員が学ぶことも多い」と佃さん。
「料理倶楽部は、担当職員だけでなく、病棟の全職員とボランティアさんの協力でここまで発展できました。利用者さんたちは、食べ物のことになると目の色 が変わり、活気づきます。人手が足りず、すべての希望者にこたえられていないのが課題ですが、今後も発展させていきたいです」と話しています。
(民医連新聞 第1569号 2014年4月7日)
 この記事を見た人はこんな記事も見ています。
この記事を見た人はこんな記事も見ています。