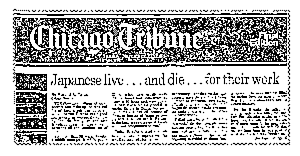いつでも元気
2003年4月1日
みんいれん半世紀(4) KAROSHI 「労過死」が死語になる日まで「労災認定に医学論争は必要ないはず」と田尻医師
ふつうの病気がなぜ労災?
「過労死」という言葉が最初に社会に向け発信されたのは、一九八二年に出版された『過労死』(労働経済社)。田尻俊一郎、細川汀、上畑鉄之丞各氏による共著です。田尻氏は民医連の医師、現在も西淀病院で診療を続けています。
「二九歳の若者の死。それが過労死問題にとりくむ出発点でした」。一九六九年、大手新聞の発送業務についていた竹林さんが、クモ膜下出血で死亡。職場の 仲間が「明日は我が身だ。合理化が竹林君を殺した」と、労災認定を求めてたちあがりました。
「細川先生(当時関西医大助教授)から僕に臨床医としての『意見書』の依頼があったんですが、そのときは、ふつうの病気であるクモ膜下出血がどうして労 災なんだと、疑問に思ったんです。労働者の現場に足を運び耳を傾けるなかで医学的問題点、運動の意味がわかってきました」
技術革新で新たな疲労が
六〇年代は、高度経済成長のまっただ中。技術革新が急速にすすみ、労働形態も大きく変化。技術革新で、企業は急速なもうけの拡大を実現しました。労働者にとってはどうだったのか?
「重労働から“重たい軽労働”に代わったのです」と田尻医師。「重労働は人間のエネルギー消費が大きい。だから長時間労働はできない。しかし、軽労働は長時間労働を可能にしたんです」
技術革新は、労働の(1)過密化、(2)長時間化、(3)単純作業や夜勤などの反生理化をもたらし、これが疲労の蓄積となって、静かに、確実に労働者の健康を蝕んでいたのです。
「過労死」が一気に注目をあびるようになる転機が、八八年四月に開催した「過労死」シンポジウムでした。
「マスコミが押し寄せて、用意していた資料が足りなくなるほどの参加者でした。高度経済成長によるツケが世に問われるほど深刻になっていたんですね」
このシンポジウムに参加した平岡チエ子さん。「シカゴ・トリビューン」紙でとりあげられた日本の優秀な企業兵士、平岡悟さんの妻です。シンポジウムの四 日後の「過労死一一〇番」で最初のベルを鳴らしました。「大阪では連絡会ができて既に七年にもなることを知って驚きました。もっと早く知ることができな かったのが悔やまれ」る(パンフ「民医連の若い友人たちへ」)と記しています。
その後、全国的に「一一〇番」がとりくまれていきました。
「急性死」から「過労死」へ
 |
| 「急性死」等労災認定連絡会結成総会で講演する田尻医師。25労組、弁護士、医師、大阪労働者の健康を守る実行委員会などから55人が参加した
|
大阪過労死問題連絡会は一九八一年七月に結成。当時は「急性死」等労災認定連絡会という名称でした。結成総会の写真(上)が残っています。横断幕は「急性死」となっていますが、報告に立つ田尻医師の後の黒板には「過労死」の文字が。
「最近資料を整理していてあれって思ったんです。このころもう『過労死』という言葉を、集会で使っていたんですね」
民医連の表現の変遷をみると、「特殊でない職業病」(78年民医連労災職業病研究交流集会)、「急性死」「在職死亡」(81年同交流集会)となっていま す。七〇年代からすでに、職業性の疲労、つまり「働き過ぎが原因となって引き起こされる死」というとらえ方をしています。
柿原正明さん(現在豊中医療生協常務理事)は七五年、ある経理課長さんの「突然死」を労災認定させるたたかいに関わりました。「探偵みたいなことをやら されましてね」。大学を卒業したての新入職員だった柿原さんは、何度も自宅や会社、かかりつけ医を訪ね、日常の労働実態や健康状態を調べました。労災認定 の決め手となったのは「奥さんの日記」。会社のタイムレコーダーには記録されていない残業や、「風呂敷残業」をしていた実態が明らかになりました。
労働者がたたかうことこそが
「仲間よ仇を」という叫びを手帳に残し、職業性ペニシリン喘息で亡くなった仲間の労災認定をたたかった遠藤富雄さんは、「先生に、『二、三人首を切られ る覚悟ができたらきなさい』といわれ、仲間と相談して三人の首切られ志願者で先生を訪ねました。結局私がほんとうに解雇され、仲間の“仇”を労災認定で とったあと、こんどは一六年九カ月、職場復帰のたたかいをしました」といいます。
「労働者が立ち上がりたたかうことが肝心なんです。弁護士や医者は、その労働者のたたかいを専門家として援助するだけです」。田尻医師は力をこめます。
冒頭で紹介した新聞労働者の「意見書」(71年)には「医学の無力のゆえに、労働者が不利益を蒙るいわれは全くない」と記しました。「労災認定に医学論争はほとんど意味がない。働きすぎたから病気になり、ひどくなり、死ぬ。そのことを明らかにするだけで十分なはず」
それから二四年後の一九九五年、長野地裁判決(前島勝三裁判長)では、「労災補償との関係で要求されるのは、医学的判断そのものではなく…」と、田尻医師の主張と同じ見解を示しています。
◇
「『過労死』なんて言葉は、一日もはやく死語になってほしい」という田尻医師。平岡さんの息子さん(当時高校生)が、「組合は死んでいる」といった言葉 が一五年過ぎたいまでも耳に焼きついています。労災認定は「過労死」の被災者・家族を救済するだけでなく、「過労死」をなくすたたかいだといいます。
文・大川敦史通信員
写真・武田博志
いつでも元気 2003.4 No.138
 この記事を見た人はこんな記事も見ています。
この記事を見た人はこんな記事も見ています。