いつでも元気
2005年12月1日
看護の現場から 戦争中の加害体験に苦しむ患者さんの話にひたすら耳を傾けた
心の重しとれ、「もう一度がんばってみる」と
「戦争を体験し、その悲惨さを直接知る方が少なくなっています。私たち医療従事者は、その生の体験を最後に聞くという機会が多いのだということを改めて認識させられました」と山口・宇部協立病院、病棟看護師長の森山美千留さん。
つらい戦争体験をもち、家族との折り合いも悪く、心身の苦痛のなかで終末期を迎えようとしていたKさん(83)の看護で、学んだことを語ってもらいました。
山口・宇部協立病院
病棟看護師長 森山美千留さん
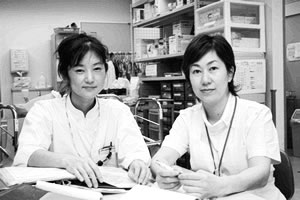 |
| 森山さん(左)と、Kさんの話を聞いた藤本さん(写真・吉田一法) |
治る見通しのなくなった終末期の患者さんの場合、闘病というより、病気を受け入れ、最期までその人らしく生きていただくということが看護の目標になります。なるべく苦痛を少なくして、穏やかな療養生活ができるよう、チームとしてとりくむなかでの経験でした。
Kさんは15歳で従軍し、戦後は炭鉱夫として約15年間働いた経験があります。60歳で肺がんのため左肺上葉を切除、65歳で慢性肺気腫のため在宅酸素 を導入。80歳でC型肝炎、肝硬変と診断され、そのころから呼吸不全が悪化。食欲不振もあり、03年5月、3度目の、最後の入院となりました。
奥さん(76)と二人暮らし。奥さんも高血圧、膝の痛みなどありましたが、夫の介護のために受診もできず、夫の施設入所を希望していました。子どもは4人いますが、市内に住む長男とは絶縁状態。他の3人は離れて暮らしています。
心身の苦痛に望みもなく
入院直後からしばらくは、慢性肺気腫による呼吸不全が悪化。一時は人工呼吸器をつけるほどでした。呼吸器 をはずしてからは、管で痰をとるのが苦しくて、「死んだ方がましじゃー! 拷問じゃー!」と嫌がり、「夢も希望もない」といっていました。奥さんはめった に面会に来ないし、来ると叱られてばかりというようすでした。
Kさんは看護師にも必要以外のことは話さず、笑顔を見せることもなかったため、医療者チームでも蕫関わりにくい患者﨟という印象でした。しかし、だから こそ看護を必要としている、どんな看護が必要か、と話し合いました。Kさんの「家に帰りたくない」「寂しい」「このまま死んでゆくのかなぁ」などという言 葉から、妻との関係が悪く、孤独感が増しているのではないかと考えたのです。
看護師に初めて語った思い
そこで看護の目標を、(1)Kさんの話す内容をさえぎらず否定せずに、ひたすら聞くことに徹しよう、(2)同時に妻にKさんのようすを伝えて関心をもってもらえるようにしよう、ということにしました。
そんなある日、看護師の藤本ひとみさんに、Kさんがこんな話を始めたのです。
( )内は藤本さんが考えたことです。
K「自分はつらいし、リハビリをするような価値もない。死んだほうがまし」(最近、息苦しさが強くなってきたので、リハビリがつらいのだろうか)
藤本「リハビリがつらいのですか」
K「リハビリとかせんでいい。女も子どももみんな殺してきた。自分がやられたらいけんからたくさ ん殺した。それも、仲間のいうことを聞いてじわじわ苦しめながら殺さんといけんかった」(あ、あ、それは戦争体験の話だな。でもそれは高齢者には普通にあ る話だし、自分で自分を必要以上に責めているのではないか)
藤本「私にも祖父がいますが、そんな話は聞いたことがありません。考えすぎなのではありませんか」
K「そんなことは人にはいえん話じゃ!」(戦争体験というのはそんなにつらくて残酷なことなのか。知らなかった)
藤本「…」
K「今こんなに苦しいのは、あのときの罰じゃ。考えるといつも眠れん。殺したもんのにらみつける目が夢で出てくる。死のうにも自分で死ぬこともできん」(そんなにつらい思いがあるから、いつも険しい表情で黙り込んで不機嫌なのか)
藤本「…」
Kさんは第二次世界大戦の加害の体験を苦しみとして抱え込んでいたのです。家族にも、誰にも話したことはなかったそうです。その孤独な思いが理解でき、 看護師のKさんに対する見方も変わりました。その時々のKさんの不満や思いを受け入れることを基本に、呼吸困難を楽にするための手だてを続けました。
この頃(10月頃)からKさんの表情が穏やかになり、夫婦関係も改善。妻にどなったりすることがなくなりました。
感謝のことばに妻は泣いた
12月になると、疼痛・しびれ感・呼吸困難などの身体的苦痛が強くなりました。しかし、「一日一日弱っていくのがわかるけど、看護師さんがようしてくれるので幸せ」といった言葉が聞かれました。妻も長時間そばに寄り添うようになり、Kさんの表情は穏やかでした。
1月末、肺炎を併発し、さらに呼吸不全が悪化。強い呼吸困難と疼痛によって、身のやり場もないほど苦しんでいました。疼痛を和らげる薬を用いると同時 に、主治医は何度か人工呼吸器の装着をすすめましたが、人工呼吸器は苦しいから二度とつけたくないと拒否していました。
救いだったのは、妻の気持ちが、「がんばって生きている夫を支えていこう」というように変化していたこと。また親子げんかで絶縁中だった二男も、Kさん の病状を知ってすぐさまかけつけ、親子のわだかまりがなくなったことです。
心配そうに、毎日病状を聞いてくる妻に、医療チームとして詳しくその日のようすを伝え、「御主人もがんばっているので奥さんも無理をしない範囲でがん ばっていきましょう」と言葉をかけることを大切にしていました。
ある夕方、夫婦2人だけで話し合ったあと、Kさんが「もう一度がんばってみる」と人工呼吸器をつけると意思表示したのです。あきらめかけていた医療チー ム全員が驚きました。病室の外で、妻は「いままで感謝の言葉なんていったこともなかったのに、初めてありがとうといってくれました」と泣いていました。
その後、数週間で全身状態が悪化。2月末に亡くなりました。
私たちが次代への語り部に
戦争体験、ことに加害の体験をもった方が死を目前にして、こんなに苦しんでおられたのか…ずっしりと重い 経験でした。軍国主義への動きが目立つなか、戦争体験を伺う機会の多い私たちは、それをしっかりと聞き、次代に語り継ぐ語り部にならなくては、ということ をKさんに教えていただいたのです。
■ご家族の了解を得て、この事例は『看護実践の科学』05年8月号に掲載されています。
いつでも元気 2005.12 No.170
 この記事を見た人はこんな記事も見ています。
この記事を見た人はこんな記事も見ています。









